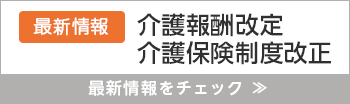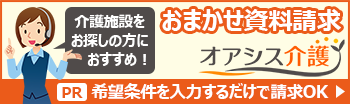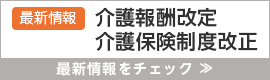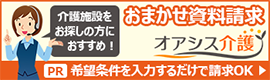要介護3は、身体機能や認知機能が低下し、特別養護老人ホームへの入居も検討できる状態です。
この記事では、要介護3と要介護2・4との違い、受けられる介護サービスと費用、要介護3と認定された事例、ケアプラン例などを紹介します。
・要介護3とはどの程度の状態?
・要介護3と要介護2との違い
・要介護3と要介護4との違い
・要介護3の介護期間は?
・介護が必要になった原因は?要介護3は認知症が1位に
・要介護3に認定された人の事例
・要介護3で受けられる介護保険サービス
・要介護3の支給限度額
・要介護3のケアプラン例
・要介護3に関するよくある質問
・要介護3のまとめ
要介護3とはどの程度の状態?
要介護3は「中程度の介護を要する状態」だっポ。
要介護3は、常に誰かの支援や見守りを必要とし、具体的には以下のような状態です。
- 身だしなみや部屋の掃除など、複雑な日常生活の動作は一人でできない
- 立ち上がりや片足での立位保持などは一人でできない
- 歩行や両足での立位などが不安定で、歩行器や車椅子を使用している
- 上下の着替えは一人でできず、助けを要する
- 排泄や入浴などは一人でできず、助けを要する
- 認知症の周辺症状(徘徊・誤食・不潔行為など)があり目が離せない
このように、介護者が支援しなければ日常生活を送れない状態が要介護3です。しかし、すべてにおいて介護が必要なわけではなく、一部の動作は自分でできる、もしくは見守りや少しの介助によってできる動作も少なくありません。
また、認知症の症状により介護の手間が増えると、要介護3の判定が出る可能性があります。理解力や判断力の低下が著しく一人で過ごすことが難しい状態では、たとえ身体機能がよくても要介護3以上の判定となるケースが多いでしょう。
要介護度は「介護の手間」をあらわしたものです。以下の表にある行為を数値化(要介護認定等基準時間)し、介護認定審査会を経て要介護度が決まります。
| 行為の区分 | 具体的な内容 | |
|---|---|---|
|
直接生活介助 |
食事 | 食事にまつわる行為 |
| 排泄 | トイレ・排泄にまつわる行為 | |
| 移動 | 移動にまつわる行為 | |
| 清潔保持 | 入浴、衣類の着脱等 | |
| 間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 | |
| BPSD 関連行為 | 徘徊に関する探索、不潔な行為に関する後始末等 | |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 | |
| 医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 | |
要介護3は、要介護認定等基準時間の70分以上90分未満、またはこれに相当する状態です。要介護ごとの要介護認定等基準時間は、以下の表で確認できます。
なお、分かりやすく数字で表していますが、介護にかかる実際の時間とは異なります。
| 要介護認定等基準時間 | |
|---|---|
| 非該当 | 25 分未満 |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護1 | |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護5 | 110分以上 またはこれに相当する状態 |
要介護3と要介護2との違い
要介護2は要介護3より介護度がひとつ軽いレベルだっポ。
要介護2は、生活の一部に見守りや介助が必要な状態です。たとえば、金銭の管理や簡単な調理などに加え、歩行や洗身などの基本的な日常生活動作にも部分的な介助を要します。
また、認知機能の低下により、薬の内服などに助けが必要なケースもあるでしょう。
要介護3は、要介護2の状態がさらに悪化し、生活を送るうえで誰かの支援や見守りが欠かせない状態です。たとえば、寝返りや歯磨きなどに介助が必要だったり、認知症による徘徊などの周辺症状があったりします。
体は元気でも、認知機能の低下によって介助が必要になるケースも少なくありません。
要介護3と要介護4との違い
要介護4は2番目に重い介護度だっポ。
要介護4は、日常生活のほとんどに介護が必要な状態です。昼夜を問わず、介護がなければ生活がままなりません。
たとえば、要介護3では歩行器や車椅子などの助けがあれば移動が可能なケースもありますが、要介護4は移動すること自体に介助が必要です。
支えがなければ座ることが難しく、整髪や洗顔などの身だしなみは、そのほとんどを介護者が行います。
要介護3の介護期間は?
介護にはどのくらいの期間がかかるのかな?
要介護3の認定を受けて、「どれくらい介護が続くのだろう」と先の見えない介護生活に不安を感じるご家族もいるでしょう。
残念ながら、要介護3での介護期間や、余命・寿命に関する調査はありません。ただし、生命保険文化センターの調査によると、他の介護度も含めた介護期間の平均は5年1カ月です。
| 6カ月未満 | 3.9% |
|---|---|
| 6カ月~1年未満 | 6.1% |
| 1~2年未満 | 10.5% |
| 2~3年未満 | 12.3% |
| 3~4年未満 | 15.1% |
| 4~10年未満 | 31.5% |
| 10年以上 | 17.6% |
| 不明 | 3% |
| 平均 | 5年1カ月 |
2021年の調査では、4~10年未満がもっとも多く31.5%、次いで10年以上が17.6%でした。介護期間は、ご本人の年齢や病状に左右されますが、長期に渡って介護する方も少なくありません。
要介護3は、日常生活の多くで常に見守りや支援が必要な状態となるため、ご家族だけで長期的な介護をするのは大きな負担です。ご家族だけで抱えこまないように介護サービスを利用すると、日々の介護負担を軽減できます。
介護が必要になった原因は?要介護3は認知症が1位に
厚生労働省がまとめた「介護が必要となった主な原因」の調査結果があるっポ。
要介護3の方が「介護が必要になった原因」は、認知症が25.3%、脳血管疾患(脳卒中)が約19.6%、そして骨折・転倒が12.8%です。
| 第1位 | 認知症 |
|---|---|
| 第2位 | 脳血管疾患(脳卒中) |
| 第3位 | 高齢による衰弱 |
要介護1~3の原因疾患の第1位は認知症です。認知症は、認知機能が低下し、生活面で障害が出ている状態を指します。
認知症は「忘れる」症状をイメージする方が多いかもしれませんが、時間や場所を正しく理解できない、道具を適切に使用できない、といった症状も出てくると、介護が必要になります。
第2位の脳血管疾患は寝たきりの原因になりやすく、発症後に何らかの後遺症が残る確率が高い病気です。そのため、生活面で支援を必要とする方も少なくありません。なかなか回復できず、要介護3の原因になっていると考えられます。
要介護3に認定された人の事例
どんな状態の人が要介護3に認定されるのかな?
ここでは、要介護3と判定された方の事例を2つ紹介します。
ただし、要介護認定はさまざまな項目や視点から判定するため、同じような状態であっても必ずしも要介護3に認定されるとは限りませんので、ご了承ください。
事例1:日常的に身体介護が必要なAさん
75歳のAさんは妻と二人暮らし。脳梗塞の発症後は、入院とリハビリテーションを経て自宅で生活しています。
歩行はできないものの、車椅子を使えば一人での移動が可能です。立ち上がりのときにふらつきがあるため、車椅子に乗る際には妻が見守り、いざというときには支えてもらうようにしています。
排泄面では、トイレでの転倒が多いため自室にポータブルトイレを設置。Aさんは、ズボンや紙パンツをお尻の半分までしか引き上げられず、トイレのたびに妻が代わりに行っています。
介護サービスは、入浴目的で週3回デイサービスを利用し、妻の負担を軽減するために月1回はショートステイを使っています。
最近は怒りっぽくなっているため、脳梗塞の後遺症の影響により相手に言いたいことが伝わらないと腹を立ててしまいます。デイサービスやショートステイでは、集団行動に支障が出ることも少なくありません。
事例2:認知症による周辺症状で目が離せないBさん
数年前にアルツハイマー型認知症の診断を受けたBさんは、長男一家と同居しています。一緒に住んでいる家族のことはかろうじて覚えているものの、近所に住む二男が顔を出しても誰か分かりません。
歯磨き粉で顔を洗ったり、誰かと話しているようなひとり言があったりします。家の中でふらふらと歩き回り自分の部屋に戻れなくなることも多く、外に出ないよう目が離せない状態です。
介護サービスは、週4回でデイサービスを利用。しかし、帰宅願望が強く不穏状態になることも多いため、職員が常に付き添っています。
家族の介護負担は非常に大きく、要介護3の認定をきっかけに施設入居を検討している段階です。しかし、本人はまだ施設に入居する気はなく、老人ホームの話になると興奮して話が進みません。
要介護3で受けられる介護保険サービス
要介護3の人が利用できる介護保険サービスを紹介するっポ。
介護認定で要介護3の判定を受けた場合は、ほぼすべての介護保険サービスを利用でき、特別養護老人ホームも入居が可能です。
ただし、福祉用具貸与(レンタル)のうち排便機能のある自動排泄処理装置の対象は要介護4以上のため、原則要介護3ではレンタルできません。
| 自宅で受ける | ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 |
|---|---|
| 施設に通う | ・デイサービス ・デイケア |
| 施設に宿泊する | ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 |
| 施設に入居する | ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・特定施設入居者生活介護 ・介護医療院 |
| 福祉用具やリフォーム | ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 ・住宅改修 |
| 地域密着型サービス |
訪問 通所 通い・訪問・泊り 入居施設 |
それぞれのサービス内容と費用を以下で解説します。費用は、1単位10円・1割負担として計算しています。
自宅で受けるサービス
以下は、要介護3の人が自宅で受けられる介護サービスの概要とその費用です。
訪問介護
訪問介護は、ヘルパーが利用者宅を訪問し、掃除や洗濯などの生活支援、食事や排泄などの身体介護、通院など目的とした乗車・移送・降車の支援をする介護サービスです。
| 20分未満 | 163円 |
|---|---|
| 20分以上30分未満 | 244円 |
| 30分以上1時間未満 | 387円 |
| 1時間以上 | 567円(30分増すごとに+82円) |
| 20分以上45分未満 | 179円 |
|---|---|
| 45分以上 | 220円 |
| 片道 | 97円 |
|---|
訪問入浴介護
訪問入浴介護は、自宅の浴槽での入浴が困難な利用者を対象とした介護サービスです。看護職員と介護職員が、体温・血圧などを測定し、持参した浴槽を使って入浴介助を行います。
1回あたりの費用は以下です。
| 全身浴 | 1,266円 |
|---|---|
| 清拭または部分浴 | 1,139円 |
訪問看護
訪問看護は、看護師やリハビリテーション専門職が利用者宅を訪問し、療養上の世話や健康チェック、診療の補助をする介護サービスです。医師の指示に基づいて行われます。
| 20分未満 | 314円 |
|---|---|
| 30分未満 | 471円 |
| 30分以上1時間未満 | 823円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128円 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問(20分) | 294円 |
| 20分未満 | 266円 |
|---|---|
| 30分未満 | 399円 |
| 30分以上1時間未満 | 574円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 844円 |
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションは、理学療法士や言語聴覚士、作業療法士が利用者宅を訪問し、リハビリを提供する介護サービスです。医師の指示に基づいて行われます。
| 20分 | 308円 |
|---|
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、医師や薬剤師・歯科衛生士などが、通院・通所が困難な利用者の元に訪問し、療養上の管理や指導を行います。療養生活の質の向上を目的とした介護サービスです。
| 医師(月2回) | 515円 |
|---|---|
| 歯科医師(月2回) | 517円 |
| 薬局の薬剤師(月4回) | 518円 |
| 管理栄養士(月2回) | 545円 |
| 歯科衛生士(月4回) | 362円 |
施設に通うサービス
以下は、要介護3の人が、施設に通って受けられる介護サービスの概要とその費用です。
デイサービス
デイサービスは、利用者が施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどを受ける介護サービスです。生活機能の維持向上、孤立感の解消、家族の介護負担軽減を目的としています。
要介護3では、以下の介護保険費用がかかります。
| 3時間以上4時間未満 | 479円 |
|---|---|
| 4時間以上5時間未満 | 502円 |
| 5時間以上6時間未満 | 777円 |
| 6時間以上7時間未満 | 796円 |
| 7時間以上8時間未満 | 900円 |
| 8時間以上9時間未満 | 915円 |
デイケア
デイケアは、利用者が施設に通い、理学療法士や作業療法士などの専門職からリハビリテーションを受ける介護サービスです。日常生活動作の維持・向上を目指します。
要介護3では、以下の介護保険費用がかかります。
| 1時間以上2時間未満 | 429円 |
|---|---|
| 2時間以上3時間未満 | 498円 |
| 3時間以上4時間未満 | 643円 |
| 4時間以上5時間未満 | 730円 |
| 5時間以上6時間未満 | 852円 |
| 6時間以上7時間未満 | 796円 |
| 7時間以上8時間未満 | 981円 |
| 8時間以上9時間未満 | 1,046円 |
施設に宿泊するサービス
以下は、要介護3の人が施設に宿泊して受けられるサービスの概要と介護保険サービス費です。
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護は、ショートステイと呼ばれる宿泊型の介護サービスです。利用者が自宅で過ごせない状態のときや、家族の不在時、家族の介護負担軽減などを目的に利用します。
要介護3の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、滞在費などが自費でかかります。
| 従来型個室・多床室 | 単独型 | 787円 |
|---|---|---|
| 併設型 | 745円 | |
| ユニット型 | 単独型 | 891円 |
| 併設型 | 847円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)
短期入所療養介護は、医療・看護などの療養上の世話を受けられる宿泊型の介護サービスです。家族の介護負担軽減を目的とした利用もできます。
要介護3の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、滞在費などが自費でかかります。
| 従来型個室 | 基本型 | 864円 |
|---|---|---|
| 在宅強化型 | 958円 | |
| 多床室 | 基本型 | 944円 |
| 在宅強化型 | 1,044円 | |
| ユニット型 | 基本型 | 948円 |
| 在宅強化型 | 1,048円 |
施設に入居するサービス
以下は、要介護3の人が入居できる施設の概要と介護保険サービス費です。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、通称「特養」と呼ばれる入居施設です。利用者は施設で生活を送り、日常生活の世話や機能訓練などを受けます。原則、要介護3以上で入居可能です。
要介護3の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、居住費などが自費でかかります。
| 従来型個室・多床室 | 732円 |
|---|---|
| ユニット型 | 815円 |
介護老人保健施設
介護老人保健施設は、通称「老健」と呼ばれる入居施設です。自宅と病院の中間の役割を持ち、リハビリテーションや介護を受けながら在宅復帰を目指します。
要介護3の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、居住費などが自費でかかります。
| 従来型個室 | 基本型 | 828円 |
|---|---|---|
| 在宅強化型 | 928円 | |
| 多床室 | 基本型 | 908円 |
| 在宅強化型 | 1,014円 | |
| ユニット型 | 基本型 | 913円 |
| 在宅強化型 | 1,018円 |
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護は、指定を受けた施設が利用者に対して、日常生活に必要なサービスを行うことです。介護付き有料老人ホームなどが特定施設にあたります。
要介護3の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、居住費などが自費でかかります。
| 679円 |
介護医療院
介護医療院は、長期的に医療を必要とする方を対象とした療養施設です。医療と介護を一体的に提供します。
要介護3の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、居住費などが自費でかかります。
| 従来型個室 | Ⅰ型(Ⅰ) | 1,070円 |
|---|---|---|
| Ⅱ型(Ⅰ) | 981円 | |
| 多床室 | Ⅰ型(Ⅰ) | 1,182円 |
| Ⅱ型(Ⅰ) | 1,092円 | |
| ユニット型 | Ⅰ型(Ⅰ) | 1,199円 |
| Ⅱ型(Ⅰ) | 1,173円 |
福祉用具・リフォームのサービス
以下は、要介護3の人が利用できる福祉用具やリフォームサービスの概要と費用目安です。
福祉用具貸与
福祉用具貸与は、利用者が福祉用具をレンタルできるサービスです。
要介護3で借りられる福祉用具は以下のとおりですが、費用は事業所や商品によって大きく異なるため、一例として参考にしてください。
| 車椅子 | 300円くらい |
|---|---|
| 車椅子の付属品 | 200円くらい |
| 特殊寝台(電動ベッド) | 900円くらい |
| 特殊寝台の付属品 | 100円くらい |
| 床ずれ防止用具 | 500円くらい |
| 体位変換器 | 100円くらい |
| 手すり(取り付け工事をしないもの) | 300円くらい |
| スロープ(取り付け工事をしないもの、段差解消のためのもの) | 500円くらい |
| 歩行器 | 300円くらい |
| 歩行補助つえ | 100円くらい |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 600円くらい |
| 移動用リフト | 2,000円くらい |
| 自動排泄処理装置(尿のみ吸引するのも) | 800円くらい |
特定福祉用具販売
特定福祉用具販売は、レンタルに適さない福祉用具を購入できるサービスです。同年度内で10万円を上限に介護保険を利用でき、超えた分は自己負担となります。
要介護3で購入可能な福祉用具は次の9点です。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具
- 移動用リフトのつり具部品
- 排泄予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器 ※歩行車は除く
- 歩行補助つえ ※松葉杖は除く
住宅改修
住宅改修は、介護が必要になっても住み慣れた自宅で生活できるように、リフォーム工事を行うサービスです。上限は一人に対し20万円ですが、転居や要介護状態が3段階以上重くなると、再度20万円が設定されます。
介護保険の対象となる住宅改修は次の5つです。なお、住宅改修に伴って必要となる改修も対象となります。
- 床または通路面の材料の変更(滑りの防止、移動の円滑化などのため)
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
地域密着型サービス
地域密着型サービスには、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などがありますが、ここでは要介護3の人が利用できる主な2サービスについて解説します。
グループホーム
グループホームは、認知症の診断を受けた方が入居する施設です。家庭的な環境のなか、少人数で生活を送ります。
要介護3の人が1日あたりにかかる介護保険の費用は以下です。この他に、居住費などが自費でかかります。
| (Ⅰ)※1ユニット | 824円 |
|---|---|
| (Ⅱ)※2ユニット以上 | 812円 |
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、「通い」「宿泊」「訪問」の3つを利用できる介護サービスです。利用者に合わせて、柔軟にサービスを組み合わせることができます。
要介護3の人が1カ月にかかる介護保険の費用は以下です。
| 同一建物に居住する者以外 | 22,359円 |
|---|---|
| 同一建物に居住する者 | 20,144円 |
要介護3の支給限度額
要介護3の上限額は270,480円だっポ。
要介護3で利用できる居宅介護サービスの上限額は270,480円です。利用者が実際に負担する額は1~3割(収入に応じる)となるため、1割負担27,048円、2割負担54,096円、3割負担81,144円となります。
上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の利用料を全額自己負担しなければなりません。
| 要支援1 | 5,032円 |
|---|---|
| 要支援2 | 10,531円 |
| 要介護1 | 16,765円 |
| 要介護2 | 19,705円 |
| 要介護3 | 27,048円 |
| 要介護4 | 30,938円 |
| 要介護5 | 36,217円 |
上記は1単位を10円で計算した金額です。地域によって異なるため、詳しくはケアマネジャーや市区町村にご確認ください。
要介護3のケアプラン例
ケアマネジャーが作成したケアプランの例を3つ紹介するっポ。
要介護3の方は、実際にどのように介護保険サービスを組み合わせて利用しているのか、3つのケアプラン事例を紹介します。なお、費用は1単位10円・1割負担で計算しています。
一人暮らしのAさん
一人暮らしのAさんは身寄りがなく、身元保証として権利擁護支援団体を利用。体は元気なものの、認知症の症状があります。近頃では認知症の症状が進み、近所の方とのトラブルや、外出すると家に戻れなくなることが増えました。
団体は施設への入居を勧めていますが、本人は納得していません。現在は、小規模多機能型居宅介護で「通い」「訪問」「泊り」のサービスを組み合わせて利用し、今後を話し合っています。
| 介護サービス | 利用回数 | 利用時間 | 自己負担額/月 |
|---|---|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 毎日 | ― | 22,359円 |
| 福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器) | 毎日 | ― | 594円 |
| 自己負担額の合計 | 22,953円 | ||
夫婦二人暮らしのBさん
夫と二人暮らしのBさんは、3カ月前に脳梗塞で半身麻痺になりました。起き上がりや移動、食事など、日常生活全般に助けが必要です。
食事は、配食サービスやコンビニなどで対応していますが、家事の多くは夫が担っています。夫はBさんの介護と家事で疲弊しているため、週末はショートステイを利用して介護負担の軽減を図っています。
| 介護サービス | 利用回数/月 | 利用時間/回 | 自己負担額/月 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護 | 4回 | 30分以上1時間未満 | 3,292円 |
| 訪問リハビリテーション | 8回 | ― | 2,464円 |
| デイサービス | 8回 | 5時間以上6時間未満 | 6,216円 |
| 短期入所生活介護 | 8回(4日) | ― | 6,296円 |
| 福祉用具貸与(特殊寝台) | ― | ― | 900円 |
| 福祉用具貸与(特殊寝台付属品) | ― | ― | 24円 |
| 福祉用具貸与(床ずれ防止用具) | ― | ― | 410円 |
| 福祉用具貸与(手すり) | ― | ― | 550円 |
| 福祉用具貸与(スロープ) | ― | ― | 50円 |
| 福祉用具貸与(歩行補助つえ) | ― | ― | 118円 |
| 自己負担額の合計 | 20,320円 | ||
息子夫婦と同居するCさん
Cさんは歩行の不安定さや認知機能の低下が見られ、目が離せない状態です。同居する長男夫婦は共働きで日中不在になるため、Cさんが一人にならないように、平日はデイサービスに通っています。
また、長男夫婦の介護負担を軽減するために、週末は月2回・2泊3日でショートステイを利用しています。自宅の廊下やトイレなどには、住宅改修で手すりを取り付けました。
| 介護サービス | 利用回数/月 | 利用時間/回 | 自己負担額/月 |
|---|---|---|---|
| デイサービス | 20回 | 8時間以上9時間未満 | 18,300円 |
| 短期入所生活介護 | 6回(3日) | ― | 4,722円 |
| 福祉用具貸与(特殊寝台) | ― | ― | 900円 |
| 福祉用具貸与(特殊寝台付属品) | ― | ― | 24円 |
| 福祉用具貸与(床ずれ防止用具) | ― | ― | 410円 |
| 自己負担額の合計 | 24,356円 | ||
要介護3に関するよくある質問
要介護3に関する疑問に回答するっポ。
要介護3に関するお金や施設入居の疑問について、ここではよくある質問に回答します。
要介護3でもらえるお金は?
要介護3を含め、要介護認定を受けてももらえるお金はありません。しかし、介護保険サービスは1~3割の少ない負担で利用できるため、1割負担なら1万円分の介護サービスを千円で利用できます。
ただし、要介護3の支給限度額である27万480円(1割負担の場合:2万7,048円)を超えると、その分は全額自己負担です。
また、自治体によっては介護手当や慰労金が出るケースもあります。たとえば鹿児島県鹿児島市では、寝たきりの高齢者を介護している家族に対して、年額9万円の手当を支給しています。
介護手当の有無や内容は自治体により異なります。詳しくは、お住まいの自治体のホームページなどで確認してみてください。
要介護3は「おむつ」「おむつ代」が支給される?
要介護3の認定を受けても、原則として介護用おむつの現物やおむつ代の支給はありません。ただし、自治体によってはおむつに関する支援があります。
たとえば、東京都世田谷区はおむつの現物支給またはおむつ代の支給を、愛知県日進市は助成券を発行しています。おむつの助成は、各自治体で支給の条件や内容がさまざまです。詳しくは、お住まいの自治体のホームページなどで確認してみてください。
要介護3は障害者認定される?
障害があると認定された人やその家族は、所得控除を受けることができます。しかし、要介護3を含む要介護認定者が、必ずしも障害者控除を受けられるとは限りません。なぜなら障害者控除を受けられる基準と要介護認定の判定基準は異なるからです。
ただし、基準の中には重複する部分もあり、身体機能や認知機能の状態によっては、要介護3の方も障害者控除の対象になる可能性があります。
以下は、障害者控除に認定される条件です。
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
(3)精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人 (8)その年の12月31日の現況で引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
※引用:国税庁「No.1160 障害者控除」 ※一部編集
要介護3なら特養に入居できる?
特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の方が入居できる施設です。
ただし、要介護3は入居条件に当てはまるものの、すぐに入居できるとは限りません。特養は人気があるため、入居まで時間がかかるケースがあります。また、申し込み順ではなく、優先順位が高い順での入居となります。
早く入居を決めたい場合は、複数の特養に申し込むなどの工夫が必要です。
要介護3のまとめ
要介護3は、日常生活全般で支援が必要な状態です。常時の見守り・付き添い、一部介助などが必要な状態で、本人の生活が昼夜逆転してしまうケースもあります。
また、認知機能の低下により、徘徊・不潔行為などで目が離せない状態も、要介護3に該当する可能性があります。
家族の介護負担が大きくなりやすいですが、要介護3ではほとんどの介護サービスの利用が可能で、特別養護老人ホームへの入居も検討できます。担当ケアマネジャーと相談して、ご本人もご家族も無理のない生活を送れるようにしましょう。
こちらもおすすめ
新着記事
ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。
ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。


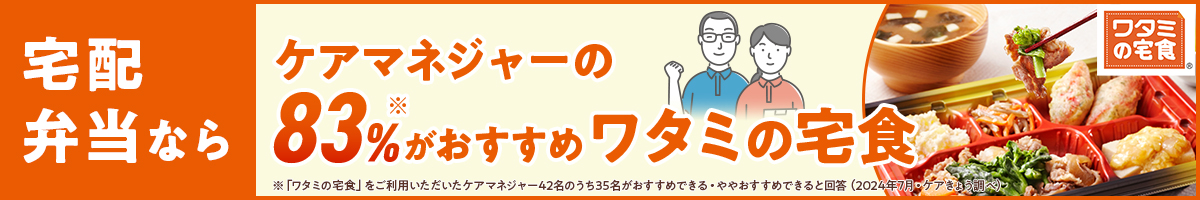
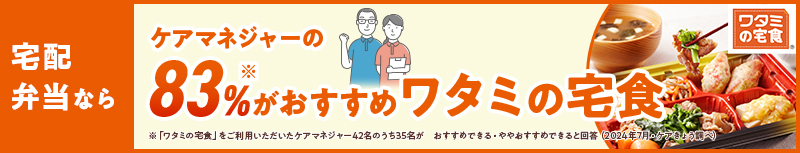
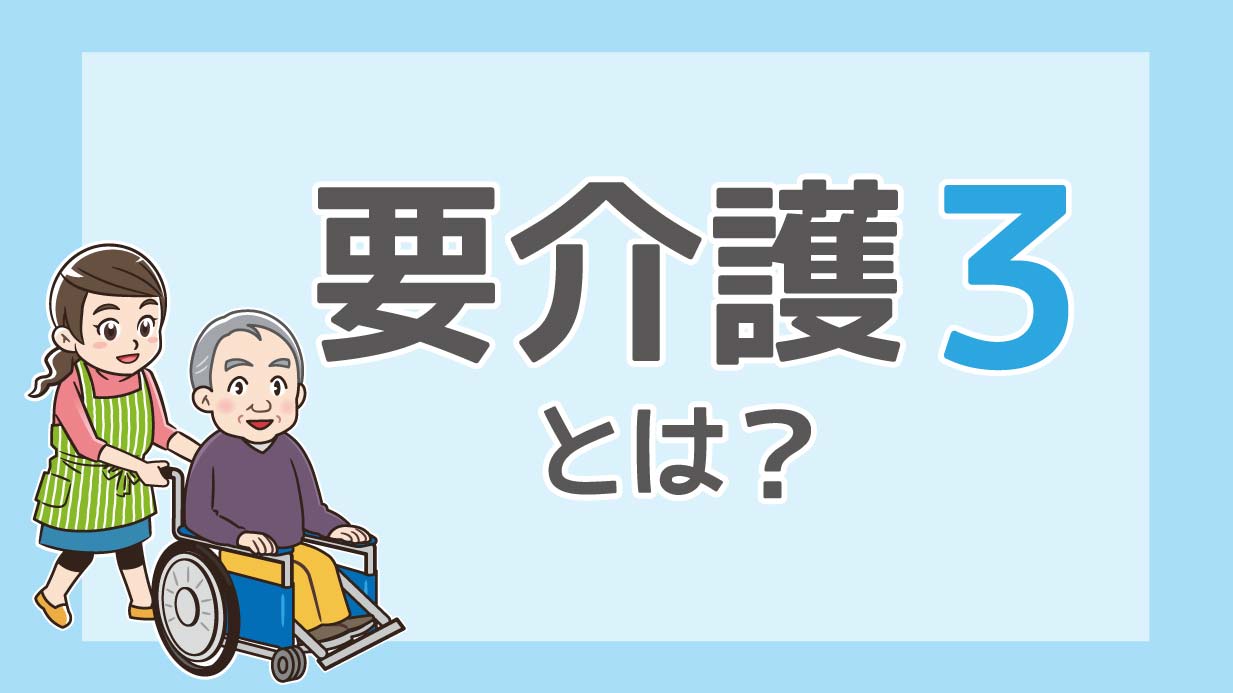








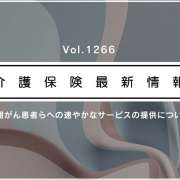


![母は回復の見込みがない…?「来週から一般病棟へ」が意味すること[介護漫画]](/storage/img/article/20250401/4251/large)